「僕は誰と生きていくべきだろうか」の中間報告。
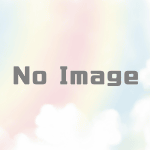
今年の裏テーマに「僕は誰と生きていくべきだろうか」というのがある。
僕の所属を振り返ってみる。
家族
友人関係
教会
ボランティア①(社会教育関係) ...
ぼくとあなたとトランプさんと石破さんとの違い。 – 考えてることを書き殴った記事。
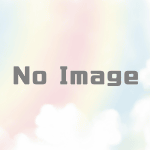
言いたいこと
こんばんは。
最近、キーボードを叩いてしっかり文を考えることがなかったのでリハビリがてら書きます。
早速、タイトル回収ですが、ぼくとあなたとトランプさんと石破さんとの違いはありません。
ぼく ...
<ソーシャルサーヴァント>宣言 – 十歩前
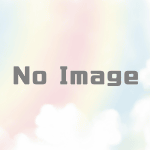
このところ、WWVの更新が落ちているのは僕が世の中に何かを言う資格があるのかが、わからなくなってきたからです。
自信がなくなっちゃった。
でも、まあ僕は僕のために、SYNHALが社会と接続し、社会的な存在であると自 ...
レジスタンスを作りたい理由。
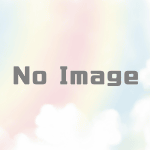
参院選が告示され1週間ほど経った。チームみらいのような政党交付金で「永田町にエンジニアチームを作る」と明言している候補者もいれば、参政党のように日々日々ヘイトを垂れ流す候補者もいる。
ベンチャー政党はよく吟味しないといけないの ...
Cool Summer.
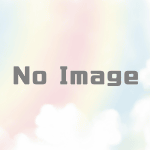
久しぶりに初恋の人の夢をみた。
というよりかは、中学校が夢に出てきた。
先週から教育業界でのバイトが始まった。人生初のノンアンペイド・ワークが教育現場なんて、中学生の俺に言ったらなんて言うだろうか。
僕 ...
生存報告
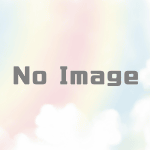
どうもどうも。
80億のSYNHALファンのみなさん。
私は生きています。
今のところ土日が用事で全滅している日々を過ごしていますが、充実はしています。
恋人でもいたら「リア充」と名乗れるのです ...
信仰が「脅かされる」恐怖
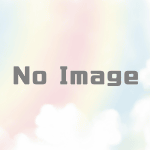
世界中の信仰者(キリスト教に限らず)に聞いてみたい。
どれだけ自らの信仰に自信があるかと。
僕はそんなにない。
神様に会った事とかないし、夢に出てきたとか声が聞こえたとかもない。
信仰は目には見 ...